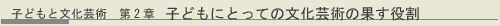| 「子どもと文化芸術?子どもにとっての文化芸術の果たす役割」 |
先ほどは、播磨さんからたいへん良いお話があって、また、この後のシンポジウムでもきちんと話し合いがなされると思いますので、
僕はアーティストの側から見た「表現教育」についてお話をしたいと思っております。
このシンポジウムは俳優座劇場創立50周年記念でやられているわけですね。
実は、10年前の俳優座劇場創立40周年のときに、うちの劇団「青年団」が初めてこちらに呼んでいただいて公演をしました。当時、こちらの支配人であった倉林誠一郎先生がまだ元気でいらっしゃって、
若手にどんどん門戸を開放しようと、僕と鐘下辰男さんと、いまは商業演劇もやっていらっしゃる和田憲明さんの3人が呼ばれて公演をさせていただいたんですね。今、
舞台から見ると俳優座劇場って「こんなに小さかったっけ?」と思うんですが、当時の私たちには、初めての300人規模の劇場、
しかも俳優座劇場という新劇の牙城のようなところに乗り込んで行くというのでたいへん緊張したのを覚えています。
この俳優座劇場創立50周年ということには他にも意味があるのです。今年は築地小劇場開設80周年でもあるので、このお話を先にしようと思います。
80年前の1924年に築地小劇場が出来ました。この劇場ができたことが日本の本格的な近代劇の始まりだと言われています。もちろんその前にも様々な近代劇の運動はあったのですが、
本格的に始まったのはここからです。これは音楽や美術など他のジャンルに比べるとすごく遅いわけです。
当時、上野には今の東京芸術大学の前身、東京音楽学校や東京美術学校という官営の大学はあったわけですが、演劇学校はありませんでした。公教育で音楽や美術はあったのですが演劇はなかったのです。
じゃ、なぜそんなに遅くなったのかということを考えなくてはいけませんが、一つには日本には歌舞伎、能、狂言という素晴らしい舞台芸術があったので、ヨーロッパのものが入ってくるのが遅れたということがあります。特に歌舞伎は17世紀の時点ですでにマーケットを持っていたという、非常に珍しい舞台芸術なんですね。17世紀当時、チケットを買って、
劇場にお芝居を観に行くというシステムを持っていたのは、ヨーロッパのほんのいくつかの都市と江戸と大阪だけでした。「チケットを買って観に行く」というのは、都市の文化が相当成熟していないと成立しないことなのですが、江戸時代には貨幣経済が非常に発達していたのでそういうシステムが生まれたのですね。マーケットを持っていると、マーケットを守ろうとする力が働くので、明治の初めの頃には、そういう力が働いたわけです。明治15年には歌舞伎を天皇に見せて、「日本の演劇は歌舞伎である」という雰囲気づくりもありました。
もう一つの側面は、1868年に明治維新があり、その後10年ぐらいの間に、政府は鉄工所、造船所、港をつくり、鉄道を引きます。日本は急速に近代国家への道を歩み始めます。
近代国家を目指す当時の日本には二つの大きな課題がありました。一つは強い軍隊をつくって植民地化されないようにするということです。そこで、義務教育が始まります。ここで問題になったのは、当時、国民の9割が農民でした。お百姓さんの生活では、まっすぐ立って歩くとか、きちんと並ぶという習慣がないわけです。そこで、そういうものを訓練する、音楽に合わせて行進ができるように、まず体育という科目が生まれ、
それに合わせて音楽という科目が生まれ、地図を書いたり読んだりできなきゃいけないので美術という科目が学校教育の中に生まれたのです。
しかしその中に演劇はなかったわけです。それはそうですね、演劇をやっても強い軍隊はつくれません、むしろ演劇なんかやっていると弱くなりますよね。一方で、自由民権運動では演劇は盛んに行われていました。字の読めない方でも演劇は分かるので、当時、演劇はプロパガンダに強い力を発揮していました。当時から演劇は反体制のものだったわけです。
もう一つの日本の課題は不平等条約の改正です。そのために鹿鳴館という建物をつくって、毎日、舞踏会を開きました。そこではじめて日本人は西洋音楽と西洋のダンス、社交ダンスに触れます。これが音楽とダンスに力を入れ始めるようになった理由です。ここでも演劇はなかったんですね。演劇をやっても別に不平等条約を改正してもらえるわけではないですからね。
ということで、日本ではまず出発点から音楽と美術は大事にされたけれども、演劇は大事にされなかった。もちろん音楽と美術の側からはそういう不純な動機で始まったために、日本の美術教育、音楽教育はだめなんだと言われます。
その後、日本は日清戦争に勝ち多額の賠償金を得ることができました。外貨が急に入ってきたわけです。そのお金で多くの留学生をヨーロッパに派遣しました。国家が組織的に芸術家や文化人、教育者をヨーロッパに派遣し、教員を養成しました。皆さんの知っている人では音楽家では滝廉太郎や、夏目漱石もそうです。
漱石は英語教育のために派遣され、森鴎外は軍人として派遣されました。このように日本の芸術教育は組織的に始まったわけですが、
演劇人は一人も留学していません。ここでも演劇はまったく無視されていました。
ではなぜ1924年に築地小劇場が建って新劇が始まったかというと、これは日露戦争に勝って、続く第1次世界大戦で漁夫の利を得た結果、「成金」という階級ができたことによるのです。民間人がお金を持ったことで、民間のお金で初めて日本人がヨーロッパに留学できるようになるわけです。その留学生のうち
の何人かに演劇の好きな人たちがいて、近代演劇が輸入できるようになったんです。その最初の1人が土方与志さんという、築地小劇場の開設に関わった人です。
ご存じの方もいらっしゃると思いますが、1922年に土方さんはヨーロッパに10年間滞在できるお金を用意して行きました。当時、土方家は男爵位で貴族だったのですが、株で儲けたお金があったんですね。
ところが1923年9月に関東大震災が起こります。関東一面が焼け野原になったという手紙が土方さんのもとに届くんですね。土方さんはびっくりして、いろいろ迷うんですが日本に帰ってくるんですね。1年間しかヨーロッパで勉強しなかったので、9年分のお金が残ったものですから、そのお金で建てたのが築地小劇場なんです。これはちょっと面白おかしくしゃべっている部分はありますが、本当の話です。
音楽や美術が国策から始まったのに、日本の演劇は偶然から始まったんです。
それには良い点もありました。1920年代は、ヨーロッパが最も幸せな時代でしたから、ダダイズムやシュールリアリズム、アバンギャルド、ドイツ表現主義などがいっぺんに入ってきて、やっている方も別に国に縛られて始めたわけではないので自由な表現ができたということがあるわけです。それが今の俳優座劇場のもとになっているわけです。
ところが1930年代になると、日本ではファシズムの嵐が吹き荒れて、演劇人は大政翼賛で協力をするか、反政府で地下に潜るか、どちらかの選択を迫られるという不幸な時代が続きました。さらに戦後、日本の新劇の中核を担った方たちは戦時中に監獄に入っていたような方たちでしたから、日本では演劇と左翼運動が非常に強い、密接な結びつきを持っていたわけです。逆に言うと、日本では政権交代が起きなかったという貧しい政治の歴史であったために、常に演劇は反政府・反体制でやってきたわけです。それが1980年代末、90年代に入ってベルリンの壁が崩壊し、
そしてソビエトがなくなって、イデオロギーの対立がなくなり、さらに日本でも自民党と社会党が一緒に政権をとるような時代になり、やっと演劇が公的な地位を得たということになってきたわけです。
|
| 変わる日本の教育 |
そういう歴史をふまえた上で、表現教育について話を進めていきたいと思います。
今では高校生がどんどん海外に留学する時代になってきました。ニュージーランドやオーストラリア、イギリスなどから帰ってきた高校生は楽しかった授業の一つに必ずドラマの授業を挙げるそうです。しかし、私たちにはそれがどんな授業なのかさえ想像がつかないですね。「ドラマの授業は普通にあるんですか」と、
今日も午前中に会った高校の先生から聞かれました。実際に欧米の先進国でドラマの授業がない高校なんてないんです。おそらくOECD加盟国で、公教育の中に演劇がないのは日本と韓国だけだと思います。韓国は今、演劇教育に熱心に取り組んでいるところですので、公教育で演劇の役割が立ち後れているのは日本だけといった状態です。
そういった日本の教育の状況にも少し変化がみえ始めました。2002年に教科書の改訂があり、僕は三省堂の中学2年生の国語の教科書の編集に関りました。僕がつくったのは「対話劇をつくろう」という単元で、授業でワークショップをやります。
少し説明しますと、僕の書き下ろした台本には、朝の教室の風景が書かれています。子どもたちがワイワイ騒いでいて、「昨日、テレビ何見た?」とか話しています。そこに先生が転校生を連れて入ってきます。転校生を紹介して、子どもたちが転校生に何か質問をします。その後、先生は用事があると言って職員室に戻ってしまい、転校生と子どもたちだけで話すという台本です。
1時間目は台本を元に、班ごとに配役を決めて簡単に練習をし、発表してもらいます。その台本には網掛けになっている部分があって、2時間目には子どもたちがそこに入るセリフを考える。朝の教室の場面で転校生に何を質問するか、転校生がどこから来たかを子どもたちが考えるんです。それから先生がいなくなった後で、何の話をしたかを考えます。3時間目にそれを班ごとに発表してもらうという、だいたい4時間もあればできる授業なんです。
このポイントは特別な施設や設備なしで教室でできることと、40分から45分の授業時間の枠組の中でできることです。
この授業は生徒にはたいへん評判が良いです。それは授業の参加率が非常に高いからです。首都圏の公立中学校では生徒の学力差がものすごくあって、塾で学校での勉強なんかはもう済んでしまっている子もいる一方で、まったく授業についていけない子もいるわけです。でもこの演劇の授業にはほとんどの子が参加できるんですね。学力の相当劣る子も自分でセリフは書きます。だれでも
でも普段しゃべっていることですからね。その後、発表がありますので、班ごとにチームワークを発揮して、恥ずかしがり屋の子はちょっとしかしゃべらないけれども、何かおいしい役をちゃんとつくってあげるんですね。
しかし教科書をつくる過程では現場の先生方からいろいろ注文や批判もありました。一番面白かったのは、「これは授業ではないのではないか」というものです。教師が教えることは何もないですからね。
この授業の目的は子どもたちだけで話している時と、子どもの中に先生が入って来る時と、先生は抜けて、転校生という他者が残っている時とで、子どもたちの話す言葉のモードが少しずつ違うことに気付いてもらうことなんですね。ところが今までの国語の授業のように、「ほら先生が入ってきたんだから、そんな言葉づかいじゃダメでしょう」と先生が言ってしまったら、この授業の趣旨はまったくなくなってしまうわけです。
授業の現場では僕はちょっと停滞している班に行ってアドバイスをするわけですが、朝の教室の風景をつくるのに「じゃ、どんな話をするかな」と聞きます。そうすると、最初は優等生的な子が出てきて、「運動会が近いから運動会の話をします」とか「宿題の話をします」とか言うんです。それはそれでいいんですが、「君はどうかな」って黙っている子に聞いてみると、「しゃべらない」って言うんです。「寝てるからしゃべらない。朝は先生が来るまでずっと突っ伏して寝ている」。「ああ、いいね、いいね、じゃ寝てる子もつくろう」となるわけです。まだ黙っている子がいるから「じゃ、君はどうなの」と聞くと「いない」って言うんです。朝は先生が来る直前にならないと来ない、
だから友だちが何を話しているかも分からない。「ああ、いいね、いいね、じゃ遅刻してくる子もつくろう」と。
そうして、いざ3時間目に発表してみると、優等生的に話し合っていた班よりも、寝ている子もいる、遅刻してくる子もいるという班の方が演劇としては圧倒的に面白いんです。そういうことも含めてコミュニケーションなんだということに子どもはすぐ気がつきます。子どもの方が早いです。
こういうことは今までの国語教育からすると逸脱した部分なのですね。しゃべらないというのは国語教育じゃないと思われているわけです。まして、教室にいないなんて想定もされていません。しかし、表現者からすれば、しゃべらない時間もコミュニケーションですね。「不在」ということもある種の表現かもしれません。
今、特に世の中では、「声に出して読みたい日本語」の方が強いわけです。しかし「声に出せない日本語」もあるわけです。出したくても出せない日本語の方が、本当は子どもたちにとって大事だと僕は思っているんですが、まだまだそういう考え方は少数派なんですね。
日本の学校教育は今まで、常にポジティブなもの、何か知識を得たり、技術を得たりして、進歩することを大事に考えてきたんです。子どもたちは進歩しないかもしれないのです。どこかに迷い込んでしまうかもしれない。でもそういう時間も大切にしてあげないといけないと、僕はずっと言ってきているわけです。
どうしても今の学校教育は即効性を求めます。即効性を求めるのなら、「百マス計算」などをやっておけばいいわけです。明らかに短期的に能力が上がりますし、子どもたちもそれを喜びます。教育のある局面でそれを使うことはかまわないと思います。しかしそれだけでは人生を生きていけないわけです。百マス計算の内容だけで、人生を過ごすことができたらラクです。でも、私たちの人生はもっと曖昧なこととか、どっちともつかないこと、判断しかねることがあって、その時その時にちょっとずつ判断して人生を前に進めているわけです。
僕は子どもたちにとって必要なものがそこにあるんだと思うんです。今後その対応力を身に付けさせられるかどうかということが、大きな課題になると思います。
もう一つ、僕が教科書をつくっていて良かったなと思うのは、この教科書のスキットには「昨日『○○』見た?」というのがあって、この「○○」には子どもたちが自分で考えた言葉を入れます。例えば、今、流行っている『あいのり』だったら「昨日、『あいのり』見た?」となります。だいたい皆さんの見せたくない番組ベスト1みたいなものが出てきます。「見てない」、「オヤジがナイター見ていた」、「ダッセー」とかというセリフも入ります。
僕が画期的だと思うのは「オヤジがナイター見てた」、「ダッセー」とかという言葉が国語の教科書に初めて載ったことです。今まで汚いとされていた言葉が載りました。これがもう一つ、僕が国語教育に果たせた大きな功績だと思っています。
今までは正しい日本語や美しい日本語があって、それを知っている教師が知らない子どもたちに教えてあげるという構図だったと思うんです。先ほどお話ししたように、日本の国家の成り立ちがそうで、知らない知識というものがど
どこか遠くにある。それは県庁所在地にある師範学校であったり、東京の教育大学だったり、あるいはパリやロンドンだったりして、そこに行って知識を習得してきた人間が戻って来て、知らない人に伝えるという構図です。要するに教育はものすごい中央集権だったわけです。
しかし今は、もうこの構図は崩れてきているのではないかと思います。今は知識や情報だけだったら、インターネットで誰でも手に入れられる時代ですね。ですから、教師には今、教えることなんか何もないんじゃないかと思えるんです
もう一つ、かつて高度経済成長の時代には、全員が成長していけたわけですから、子どもも教師や親の言うことを聞いて、自分の能力に合わせて、良い学校に行って、良い企業に入って、企業の中で上司の言うことを聞いていれば、だいたい安定して幸せになれました。今はもうそんな時代ではないわけです。どんな大企業に就職しても、
その企業がつぶれないとは限らない。僕と同世代の人たちで、給料のほしい人は証券会社に行き、安定のほしい人は銀行に行きました。80年代はそういう時代でした。ところが、僕と同期で銀行に就職した友だちで、就職したときと同じ名前の銀行にいる人間は1人もいないです。
僕は大学時代から「青年団」という劇団にいて、ここはいまだに名前が変わってないです。一番安定してないはずの僕が一番安定しているというように、かつての価値観はもう通用しなくなっているのです。子どももそれを敏感に感じ取っているのです。私たちの世代は教師に「これを覚えておかないと、
お前が損するんだよ」という言い方をされて、いろんなことを覚えさせられましたが、今は「損する」根拠はないです。これを覚えていなければ生きていけないなんて知識は何もないです。あったとしても、それは自分で手に入れることができる時代です。
そうだとすると教師の役割はまったく変わってきます。知識や情報を与えるのが教師の役割ではない。あるいは教科書の役割ではないということになってくるのです。
三省堂の教科書が成功したのは、「教科書を教える」のではなくて、「教科書で教える」としたことです。教科書のなかには「こういう教え方もあります」、「こういう教え方もあります」とさまざまなプログラムが書いてあり、それを使って先生が自由に教えることになっています。
|
| 競争社会は終わった |
最近の20年から30年の間、「表現教育」の必要性が強く言われ、国語教育のなかにディベートとかスピーチとかの音声言語教育(話し言葉の教育)の手法が急速に入ってきました。
しかし私たち表現に携わるプロフェッショナルの側からは、これでは日本の表現教育は、子どもたちの首を絞めて「表現しろ、表現しろ」と強迫しているようにしか見えないです。そういった表現教育に熱心な先生には後ろからそっと肩をたたき、「いや、まだその子は表現したいと思っていませんよ」と言ってあげたい心境です。
日本はもうすごい競争社会ではなくなってきました。確かに「受験」はあり、受験産業が煽っていますが、厳密に言えばだれでも大学に行けるし、私たちの世代のような競争社会ではなくなってきています。ですから過激な競争をする意味もなくなってきているわけです。子どもたちは競争に勝って幸せになれるとは限らない時代に育っているんです。
子どもも少ないですし、みんなやさしいですから、お互いに分かり合ってしまう。今の子どもたちの社会は分かり合う柔らかい社会なんですね。
今の子たちは単語でしかしゃべらないですね。「ケーキ」とか、「宿題」、「先生」「夏休み」・・・。でもこれは子どもが悪いのではなく、「ケーキ」と言うと、ケーキを出してあげるような家庭に育ったからで、昔みたいに兄弟が多ければ、ケーキを食べたいのか、ケーキを焼きたいのか、ケーキをぶつけられたいのか、
きちんと言わなきゃいけなかったんですけれども、今の子どもはそれを言う必要がないのです。
それから中学、高校では教室の中でも親しい友だちとしか話さない。これは皆さん、信じられないことかもしれませんが、ずっと同じクラスなのにまったく名前を知らないという子が本当にいるんです。今年、僕の地元の都立駒場高校が高校演劇の全国大会に出るんですが、その作品は主人公が同級生の女の子の名前をずっと知らないで、
「君さ・・・」とごまかして言うことが一つのギャグになっていました。今の子どもたちには普通のことのようです。
コミュニケーションがすごく閉じたところでしか行われなくなっているんですね。
そういう子どもたちに対して、「表現教育」を行うということは、かつての競争社会のなかで行ってきたこととは質が違ってこなくてはいけないだろうと思うんです。
このように子ども時代は温室のようなコミュニケーションのなかで育ってい
るのですが、社会に一歩出れば、グローバルスタンダードと言われる強い説明責任を求められる世界があります。僕は決して子どもたちの表現能力が衰えているとか、コミュニケーション能力が衰退しているとは思わないのですが、このギャップが大きくなっているのを感じています。
昔だったら外国人と話すなんて外交官とか商社マンとかごく限られた人だったわけですが、今は隣りにアメリカの人が住んでいても、イランの人が住んでいても全然不思議じゃない時代ですね。しかも政治の話や経済の話をするんじゃなくて、その人たちにゴミの出し方や布団の干し方について話さなきゃいけない時代なんです。
でもそんなこと学校では習わないですね。価値観のまったく違う人にどう自分の生活のスタイルを説明するかなんて訓練は全くしなくて、いきなり社会に放り出されるわけです。そうすると、心の弱い子や、引っ込み思案な子は心を病んでしまったり、引きこもってしまったりするのは当然のことだと思います。
発達段階に応じて、自分と異なる価値観の人と出会う経験をさせてあげなきゃいけないのですが、今までの学校教育のプログラムのなかにはこれが全くなかったわけです。
|
| 「伝わらない」から表現する |
本来、表現教育は、動機があって表現するものです。その出発点は「伝わらない」という経験だと思うんです。「ケーキ」と言ったらケーキを出してもらえたら、表現する必要がないわけです。
僕はよく高校生の演劇の指導に行って、演劇をつくるのはラブレターを書くようなものだと言います。俺はお前のことがこんなに好きなのに、何でお前は俺のことが分かってくれないんだという気持ちがラブレターを書かせて、いろいろ工夫をさせると思うんです。最初からお互いに好きだったら、抱き合っていればいいわけで、ラブレターなんか書く必要はないわけです。
このように、伝わらないという経験をして、初めて伝えようという気持ちが起き、そこからいろんな技術に対する欲求や信頼が生まれてくるのです。そういうものを一切抜いて、いきなりスピーチだとかディベートだとかと技術だけを教えても、表現力は身につかないのです。そこが日本の表現教育に完全に欠如しているところだと思うわけです。
伝わらないというのは孤独ということです。孤独、寂しさ、死、障害を持つ
可能性、老い、病にかかる、そういったネガティブなものは、今までの日本の学校教育から一切排除されてきましたが、そこをきちんとやっていかないと、「表現教育」だけやっても効果は薄いのではないかと思います。
それは何も難しいことではなくて、例えば農作業体験をすれば、自分の思い通りにならないことがたくさんあることが分かります。老人ホームにボランティアに行くとか、障害者施設で一緒に芸術活動をするとか、自分とまったく生き方が違う、しかし自分もそうなる可能性のある人たちに接することで、
ずいぶん表現に対する考え方が違ってくると思うんですが、そういう機会なしに「表現教育」だけを進めても、意味がない。
今は都心部ですと公立の小、中学校では、1学年1クラスというところもあります。小学校1年から中学校3年までずっと1クラスというようなところもあるわけです。しかも1クラスが25人とか30人で、教育環境は良く、皆仲良しです。これはとても良いことですね。ところがこれは表現教育では良いことではないんです。
「はい、太郎君、前に出てきて3分間スピーチしてください、みんなもよく聞いてるから」って言うんですが、その太郎君のことはみんなが全部知っているんです。ですから、彼の話すことはスピーチじゃないですよね。何か自分の伝えたいことがあるからスピーチをするのに、みんなと同じですから伝えたいことは何もないんです。これでは表現教育にはならないです。
|
| 異文化・職業を体験できる表現活動 |
僕は今、三省堂で小学校の教科書の編集に関っています。これは5年後の採択に向けて準備されているものですが、編集委員には30代、40代の現場の国語の先生や、外国人の子どもたちの日本語教育の先生や音楽の先生も入っていて、内容は相当画期的なものができるのではないかと思っています。
この前の編集会議で僕が提案した授業の一つに、一年生の最初の国語の授業では、教室にあるものの名前を全部、自分たちで決めるというものがあります。例えば「これは世間では黒板と呼んでいるけれど、うちの教室ではどう呼ぼうか?」から始まります。今、東京近郊の小中学校では、中国人子弟や帰国子女、
いろんな子どもがいます。その子たちに「何て呼んでた?」と聞きます。そのなかで子どもたちが一番カッコイイと思うものを選べばいいんですね。月
「黒板」と呼ぶけれど、水曜は「ヘベレケ」と呼ぶことにしようでもいいわけです。それを子どもたちが決めます。
これには二つの案があって、一つはよそではこう呼ぶけれど、教室ではこう呼ぶと教えようという案です。もう一つは、よそで何て呼ぶのか教えないでみようという案です。子どもが痛い目に遭ってから教えるという、ちょっと極端な話ですが、そのくらい自由な教科書を作ろうということで進んでいます。
高学年の教科書では村上龍さんの著作『13歳のハローワーク』の国語版のようなもので、いろんな職業の言葉を集めてきて、それを子どもたちで演じてみるというようなことが企画されています。
これは実際にフランスで経験したことですが、パリ近郊の劇場の芸術監督をしている友だちの演出家のホームパーティーに招かれて行ったら、その演出家が「今日はオリザの『東京ノート』をうちの子どもたちのワークショップでやったんだよ」って言いました。『東京ノート』というのはおとながやっても難しい芝居なんです。
そこは不法滞在の労働者が多い、サンドニという非常に多国籍の町で、通りを歩くと半分以上がアフリカ系の人です。そういう町なので、そこの劇場でやる子ども向けのワークショップは、毎回、アジア、アフリカの劇作家の作品を演じてみるんですね。別に解説も何もしないんだけれど、「今日は日本人を演じてみましょう」、「今日はアルジェリア人を演じてみましょう」、「今日はカメルーン人を演じてみましょう」といったワークショップなんです。
しかしそのことによって、「ああ、日本人ってこういうことをしゃべっているんだ」、「あまり私たちと変わらないな」、「こんな表現の仕方をするんだ、変なの!」とかを感じてもらう、というワークショップなんですが、これはとても大事なことです。
今、僕は幼児から高齢者まであらゆる年齢の人たちにワークショップをやっていますが、中学生が一番難しいと感じています。自我が芽生えてくる時期ということもあるんですが、それだけではなくて、どうも小学校5年生ぐらいから中学1年生ぐらいにかけて、学校も親もみんな日本の社会全体が、急速に子どもに社会的な役割を押しつけていくんですね。それは男の子らしくとか、女の子らしくだけでなく、成績の良い子は良い子なりに中学受験とか、
成績のそんなに良くない子にはスポーツをがんばれとか、親もほとんど無意識なのでしょうが急に押しつけ始めるんです。
その辺で子どもは戸惑っている感じがします。しかも今の子どもは素直ですから、周囲の期待に応えようとして、自分をがんじがらめにしばっているのを感じます。
本当はもはや競争社会じゃないわけですから、どんなに学校の成績の良い男の子でも料理が上手だったらコックになればいいじゃないですか。でも、おとなの方は成績の良い男の子はやはり未だに、良い高校に行って、良い大学に行って、大企業に就職するのだと思っていて、子どもにそれを無意識に押しつけていといった雰囲気があるんですね。
そこでこの教科書では小学校5年、6年の子どもたちにいろんな職業を、演劇を通じて経験してもらおうと考えているのです。これをなんで国語でやらなければならないのだろうと疑問に思うわけですが、今は国語でしかできないのです。
これはちょっと蛇足ですが、僕は国語という授業自体がもうなくていいと思っているんです。少なくとも小学校4年生ぐらいまでは、表現という時間と、日本語という時間に分けたほうが良いと思っています。表現の方には美術も音楽も、今は体育にあるダンスも、国語教育の表現の部分も入れる。日本語は、本来は日本語ではなくて「言葉」という授業にしたほうが良いと思いますね。そこで英語と韓国語と日本語をいっぺんに教えると、日本語が世界の言語のうちの一つだと、
子どもたちも相対化できるのではないか、というのが僕の主張なんですが、しかし、
これが実現するには、まだあと30年から40年かかると思いますので、今はやれる範囲でやろうと思っています。
|
| 障害を持った人とのワークショップ |
今日は最初に播磨さんのお話があったので、僕も少し障害者向けのワークショップから学んだことを少しお話したいと思います。
僕が障害者とのワークショップを始めたのは5、6年前からです。宮崎に「アートステーションどんこや」という福祉作業所がありまして、
ここは個性の強い人たちが集まっていて面白いところです。そこの若い所長さんから、演劇のワークショップをやってくれと言われました。
僕は障害者を対象にしたワークショップはまったく経験がなかったので、最初は非常に戸惑いました。だいたいそんなことができるのかと思ったんですね。
障害者に対するワークショップでは音楽が一番多いですね。音楽は叩けば音が出ますし、美術は知的障害の方でその才能を持った方は多いですから作品にもなりやすいのですが、演劇は言葉を使うので難しいと思います。
どうしようかと思ったのですが、作業所の方たちは普段どおり、できるだけいつもやっているワークショップをやってくださいと言われるので、普段どおりやりました。そうするといくつか面白いことが出てきました。
例えばウォーミングアップではいろんなゲームをやるんですが、作業所の人たちはすばやく体を動かすようなことはできませんので、「震源地ゲーム」というのをやりました。これは輪になって、真ん中にオニがいて、震源地になる人が別にいます。この震源地の人が体を動かすと、周りの人がそのとおりを真似して体を動かします。オニのスキをついて震源地の人は動きを変え、周りの人も変えるんです。オニがその震源地の人を当てるというゲームです。
震源地の人がうまくオニのスキをついて見ていないときに変えるとなかなかこれが当たらないというゲームで、相手の動きをじっくり観察するというのが、この演劇ワークショップの一つの趣旨なんです。
これを障害者の方とやったとき、ものすごくウケました。全員が初めてだったのですが、ものすごく喜んで、明日からラジオ体操の代わりにこれをやろうというぐらいにウケたんです。
そこには脳性マヒの方が多かったんですが、脳性マヒの方が震源地になるとまず当てられないですね。動きが特殊で、しかも脳性マヒの人にはその通りの動きは真似られなくて、みんな動きが滅茶苦茶になるんです。滅茶苦茶なんだけれど、ある種の統一感がある。ですから健常者がオニの場合は絶対に当てられないんです。
整理すると、ここでは敢えて「変な動き」と言いますが、障害者の「変な動き」を見て、健常者が右往左往する。それを見て障害者が笑うという構図、こんなことは普通あり得ない非常に「変な構図」になってしまったんです。
これは私たちにはとても貴重な体験でした。あとで施設の方々と話したんですが、これはもしかすると、福祉ボランティアをやろうとしている人たちの初期の訓練にとても良いんじゃないかということになりました。私たち健常者は普通、脳性マヒの人をじっと見るなんてことはまずできないですね。そんなことをしたら失礼だと思います。
でもこれはゲームなので、ずっとお互いに見つめなきゃいけない。それがあるルールのなかで普通に行われて、しかもみんな楽しい。
また、3人1組で大きなボールを想定して投げるというゲームをやりました。これは実際のボールではなくて、ボールがあるつもりで、架空のキャッチボールをします。もし実際に大きなボールをうまく投げるとか、遠くに投げるというゲームだったら、障害者がチームにいることはハンディになります。しかしこれは演技で、どうやってこのボールを投げているかのように見せるかを競うわけですから、どれだけリアルかを競うのなら、
障害者がいることはハンディではなく、ただの前提条件なんです。
これは社会にとっても重要なことです。私たちは「障害はハンディではなくて『違い』なんだ」と口では言いますが、実際の経済生活ではそうはいかない。やはりハンディになることが多いですね。しかし演劇というフィクションのなかでは、「違い」なんだと実感できるんです。
こういうことを子どもたちの発達段階において経験させるのはとても大事なことなんじゃないか、できるだけ若いうちにこういうことをたくさん経験しておくことが必要なんじゃないかと思うのです。
|
| 芸術文化施設の役割 |
表現教育を進めていくには学校だけでは限界があります。欧米では地域の劇場や大学が施設を提供したり、人材を派遣するのは普通です。しかし、日本ではその機能が非常に弱いです。
私が芸術監督をしている埼玉県富士見市には市立中学が6校ありますが、今年はそのうちの4校で、僕が国語の授業を行いました。来年はたぶん6校全部になると思います。
僕はこれを10年、20年と続けると、全市民が一応は演劇をやったことがあるということになり、これは大きなことだと思っていたのです。ところが、実は富士見市というのは池袋から電車で25分ぐらいのところに位置していて、
ふじみの駅の周りには30階ぐらいの高層マンションが林のように建っているんです。そのマンションの子どもたちの6割は私立中学に行っていると知って、浅はかだったと気付きました。
この問題は今まで顕在化してこなかったのですが、これはコミュニティにとってもたいへん重要な問題です。今、ご存じのように地域の人のつながりはかろうじて学校を通じてできているのですね。「○○ちゃんのお母さん」ということ
ことで知り合いになっているんです。ところが子どもが公立中学に通っていないと、そのネットワークからも外れているんです。こういったことは地域にとっても自治体にとっても非常に問題です。
それで、今度は私立中学に通っている子どもたちが通いやすいような日程でワークショップをやろうということになるんです。これが本来の地域の文化行政あるいは芸術施設の役割なのですが、そういうことをやっている劇場は非常に少ない。
大学もそうですね。私は今、相模原市にあります桜美林大学に勤めていますが、来年度から相模原市の産業総合高校の「コンテンツ産業」という授業では、私が責任を持ってダンスと演劇のプログラムを編成し、講師を派遣し、
大学生がボランティアとしてサポートするということになっています。こういうことはアメリカの大学では普通のことなんですが、日本の大学ではほとんど行われてないですね。
医学部を持っている大学は大学病院を持っていますが、それは単なる研究施設ではなくて、きちんとその地域の医療や健康に責任を持つというのが大学医学部の役割です。同じように表現活動についても、表現教育の過程を持っている大学は、その地域の芸術表現に対して責任を持つべきなんです。しかし、日本ではそういう感覚がほとんどありません。
それはなぜかと振り返ってみると、日本の芸術教育というのは、先ほど言ったようにある種の偏った国策によって始まったものだからです。決して国民や市民のために芸術文化があったわけではないんです。その根本を変えていかない限り、なかなか事態は変わっていかないんじゃないかと思います。
|
| 産業構造の転換 |
子どもたちに何で芸術教育が必要なのかというときに、やはり産業構造の転換に大きな理由があると思うんです。
先ほども言いましたように、今は人口の6割から7割がサービス業に従事していますが、残念ながら教育の体制も国家の体制も経済の体制もすべてまだ工業立国のままなんですね。
工業立国だったらば、上司の命令をきちんと聞く社員が良い社員なのです。しかし、これからはサービス業ですから、1人1人の個性や発想、
柔軟性、コミュニケーション能力が重要になってきます。日本は消費社会ですから、は第1次産業、第2次産業に従事する人にとっても重要なことなんですね。
この前NHKニュースを見ていて面白いなと思ったのは、ある勲章をもらった果物作り一筋という果樹園のおじいさんに、「農業で一番大切なものは何か、今の若者に伝えたいことはありますか」と質問すると、普通なら職人的な答えが返ってくると思っていたんですが、そのおじいさんは「消費者の気持ちを汲んでつくることが大事です」と答えていました。すでにそういう社会になっているのですね。
また、一昨年は雪印を始め、いろいろな食品会社の不祥事が続きましたね。あの時会社は謝り方を間違えました。もちろんやったことも悪いのだけれども、その後の対応がまずくて、事件がどんどん広がっていき不買運動がおこらなくても、消費者が買わなくなり、雪印ほどの大きな会社が潰れる寸前までいきました。
そういう時代なんです。今までのように良いモノを作って、販売網がしっかりしていたら売れるという時代ではなくて、消費者が商品を選ぶ消費社会になっているんです。昔は牛乳は配達されていましたから、そう簡単に銘柄を変えなかったですが、今はスーパーで買うので、ちょっとイヤになったら、みんないっぺんに違うメーカーのを買います。それを消費社会と言うのです。ですから企業人全員が消費社会の感覚を持っていないといけないですね。
味の素という会社が総会屋事件で不祥事を起こしたとき、その後の対応として社会貢献課を作りました。もちろんこれはイメージアップをはかるために作ったわけですが、社員全員がボランティアを経験できるような組織にしました。なぜなら、「企業人間」は企業の利潤だけを追求していって、外が見えなくなってしまい、上司の命令が間違っているとわかっていても聞いてしまう。自分のノルマを達成するためには、
犯罪性のあるものでもやってしまう。そういったことを避けるためには、市民的な感覚、消費者的な感覚を持った、重層性のある人間を作らないといけない、人間1人1人が変わっていかないとダメなんだというふうに考えたわけです。
月曜から金曜までは企業人として振る舞っていているのだけれど、例えば土曜、日曜は、ボランティアでサッカーを子どもたちに教えているときに、ボールを蹴りながら、子どもが「おじさんは会社で何をしているの」と聞かれたら、自分が会社で何をしているかをきちんと説明できるような人材になっていかなきゃいけないわけです。今までは会社の中で、外で接触するのは広報部とか広報課
広報課の人たちがやってくれていたわけですが、消費社会ではそうはいかない。1人1人が消費者と向き合うような存在になっていくわけです。このように社会全体の1人1人のコミュニケーション能力が高まっていくことが求められている社会になりつつあるんですね。
|
| コミュニケーションのあり方を変える |
子どもの表現教育はイギリスで一番発達しています。文化行政もイギリスやフランスが一番発達しています。しかしこれは何百年も前から発達していたわけじゃなくて、ほとんどが第2次大戦後からなんですね。イギリス政府が演劇に直接支援し始めたのも戦後です。学校教育もそうです。
どうして始まったかというと、イギリスやフランスは植民地をどんどん失っていく過程で、植民地からどんどん人が帰国してくる。それと一緒に植民地の支配階級の人たちも難民のようにしてどんどん入ってくる。50年代、60年代には、こうしてイギリスやフランスはどんどん多国籍化していきます。そういう新しい、多国籍化した、他民族化した社会でコミュニティをどうやって再編成するかというときに、
これはもうスポーツも含めた芸術文化に頼らざるを得なかったんです。一番象徴的なのは、1998年、フランスでのワールドカップ戦のときに、フランスが優勝するんですが、このチーム11人の先発メンバーのほとんどが移民の子どもだったのです。両親ともがフランス生まれの選手はたぶん1人もいなかったでしょう。
日本はどうかというと、もちろん日本が欧米とまったく同じことをする必要はないのです。違う選択肢もあると思います。実際に日本がヨーロッパと同じように移民を受け入れられるかどうかも分かりません。しかし他方で、日本は今後、年間40万人から50万人の移民を受け入れていかないと年金制度も全部崩壊するだろうという統計上からの予想もあります。
どちらを選択するかは日本の大きな判断ですが、もしさまざまな人を受け入れていくという選択をするとすれば、芸術文化や表現教育の役割は小さくないでしょう。ですから、それを教育の中核に置かない限り、多用な価値観を認める新しい社会は生まれてこないだろうと思います。
そこまでの判断は下さないにしても、今まで話してきたように、これからは子どもたち1人1人の価値観がバラバラになっていく時代になるわけですから、それを認め合って、その中でうまくやっていく社会を作っていかなきゃいけないわけです。
今までのように「一致団結」とか、「心を一つに」とか、価値観を一つにする方向の社会から、価値観はバラバラでいい、バラバラの人間がうまくやっていく社会に変えていかなきゃいけない。これは日本人にとって大きな精神構造の変換が迫られるのですね。今まで日本人は心から分かり合えないとコミュニケーションじゃないというふうに考えてきましたので心のふれあいとか、心から信じ合える関係を目指してきました。
それは理想としては良いですが、外国の人と初めて出会って、いきなり心から分かり合うなんてことはできないです。
また、私たちはイラクの子どもたちの気持ちは分からないです、なぜなら私たちはどんなに日本で貧乏をしていても世界の中で1割の豊かな国の中に入っているわけです。こんな中で育っている人間が貧困で苦しんでいる人の傷みを理解するのは大変なことです。大変なんだということを理解した上で、どうにかして彼らと共有できるものを見つけていくというふうに、コミュニケーションのあり方自体を変えていかなきゃいけないわけです。
僕は日韓の交流に20年ほど関わっていますが、日韓の問題で強く言ってきたことは、全員が全員、韓国を好きになってもらう必要はないということです。今はたいへんな韓国ブームでありがたいことですが、これは非常に特殊な状況であって、本来、みんなが韓国のことを好きになる必要はないわけです。しかし、韓国は日本の隣りにあるという地理的な関係は変わらないわけですから、隣りにいる人とどうにかしてうまくやっていくということが本来のコミュニケーションなんです。
心から分かり合うことはもちろん理想だけれど、理想だけを追い求めていたのではコミュニケーションはできない。そのとき、そのときに応じて、やれることをやっていくのがコミュニケーションで、私たち大人は普段そのようにして人と付き合っているんです。それを子どもには理想を押しつけて、心から分かり合えなんて言うのは大人の傲慢な態度だと思うわけです。
ですからこれからは異なる価値観を持った人たちがどうにかしてうまくやっていく、そういうコミュニケーションをまず子どもたちに身に付けてもらう。そういう表現教育が必要になってくるんじゃないかと思います。
|
| 10年、20年後を見据えた教育を |
演劇は2500年前にギリシャで生まれました、それはギリシャで民主制が生まれた時期なんですが、その民主制が生まれた時期に、おそらくアテネの人はとても戸惑ったと思うんです。それまでは王様や貴族が決めてくれていたことを全部自分たちで決めなければいけないことになったわけですから。ところがこの市民たちはバラバラでした。1人1人の価値観も何もかも違っていました。これで話し合えと言われても、声が大きい者や力の強い者が勝つことになって、また元の木阿弥じゃないかと考えたと思うんです。
そのときにギリシャの人々は、異なる価値観を摺り合わせる方法として二つのことを人類に遺産として残してくれました。一つは哲学で、弁証法と呼ばれるものです。Aという概念とBという概念があったときにCという新しい概念を生み出すというものですね。
そしてもう一つが演劇だったんです。当時のアテネ市民にとって、演劇祭への参加は権利であると同時に義務でもありました。演劇をやらなきゃいけなかったんです。そこでは、集団の中で言葉や感性を摺り合わせる能力を身に付けたんです。これは別にギリシャだけのことではなくて、かつて日本の村落共同体でも伝統芸能の継承とか、農村歌舞伎とかでお祭りの前になると1カ月、2カ月間も合宿をして、そういうことを学んできました。
そのなかでは、学校教育から排除されてきた闇の部分、孤独とか寂しさ、あるいはセックスのことも含めた闇の部分をちょっと年上のお兄さんたちから教わってくるような伝統的な習慣があったわけです。しかし、今、日本にはこの地域共同体はもうないんですね。そしてそこに戻ることもできない。そこにはいろんな因習や差別も含まれていましたから、僕はそこにもどった方か良いとは思いません。
だとしたら、地域の共同体のシステムが担っていたある種の機能を私たちがもう一度人工的に作り出さなければいけないのです。その役割を、劇場であり、大学であり、あるいは皆さんが関わっているNPOが果たさなくてはいけないと思います。
最後に、俳優座劇場でこういうシンポジウムをなさるのは初めてだそうで、たいへん素晴らしいことだと思います。今、遅ればせながら多くの日本の劇場は鑑賞施設から地域に役立つ劇場へと変わろうとしています。そういう時期に表現教育はどういう方向に行くのか、大きな転換点にあると思っています。依然として教育界はポジティブで、成果の上がるものに目が向きがちですが、
私たちは地道に、今の子どもたちが10年後、20年後、社会に出たときに役に立つものは何か、何が彼らにとって幸せなのかという視点で教育をしていきたいと思っております。
|